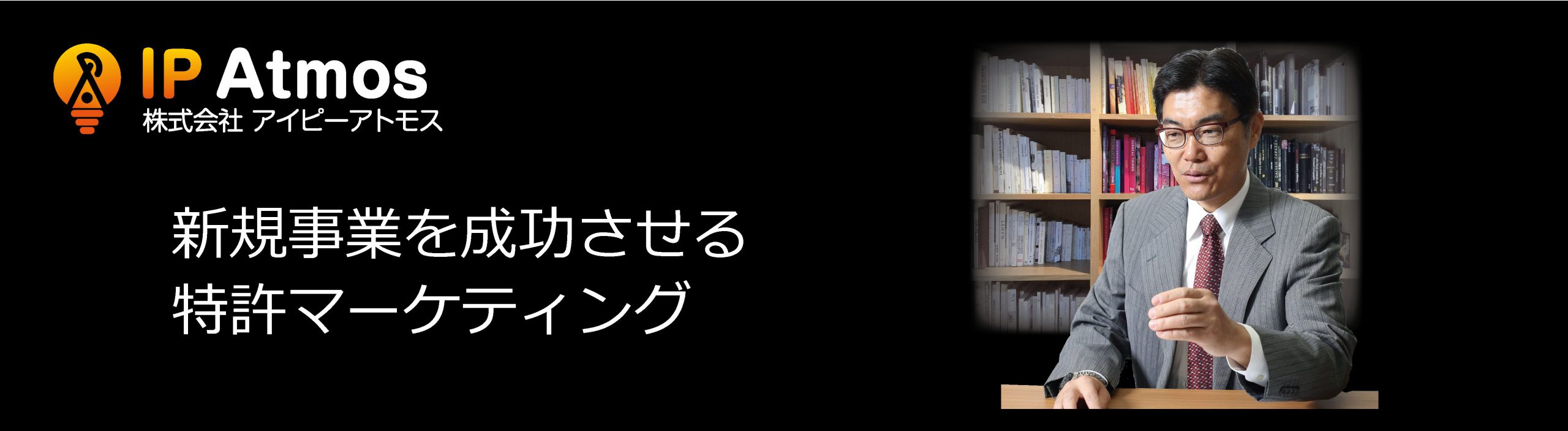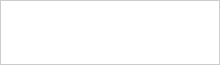売れ行き低迷で悩んでいる機械メーカーの「スキマ商品・ニッチ市場」の見つけ方
~C社(お茶用加熱乾燥機械メーカー)の事例~
こんにちは。株式会社アイピーアトモス代表取締役の座間正信です。
弊社では、特許情報と市場情報とを組み合わせて、競争相手が少ない「スキマ商品・ニッチ市場」を見いだす手法を開発し、その手法を用いて「勝てる市場の探索」と「新商品開発の支援」を行っています。
今回はお茶用の乾燥機械の製造販売をしているC社の事例を紹介します。
お茶農家の戸数は減少し、大規模化が進んでいる
 お茶は、生葉の収穫後、産地で荒茶に加工され、消費地において製茶にブレンドして販売されます。荒茶の段階では約900億円の産業規模となります。
お茶は、生葉の収穫後、産地で荒茶に加工され、消費地において製茶にブレンドして販売されます。荒茶の段階では約900億円の産業規模となります。
主要産地は、
①静岡県
②鹿児島県
③三重県
④京都府
⑤福岡県
であり、上位3県で全国の栽培面積の約7割を占めるほど寡占が進んでいます。
- 栽培面積、生産量、生産者数共に減少
最近のお茶離れにより、栽培面積は緩やかに減少し続けています。生産量は、緑茶飲料需要の増加を受けて平成16年産が10万トンを超えるなど一時期増加したものの、その後減少し、近年は約8万トンで推移しています。(図2)
また、お茶農家の経営面積は規模拡大が進んでおり、特に鹿児島県では規模拡大が顕著となっています。
その結果、農家数は激減しており、平成12年には5万3千以上あった農家が、平成27年には約2万件と半分以下にまで減少しています。
- 減少するお茶農家向けの機械メーカーがとりうる2つの戦略
 お茶の価格については、ペットボトル緑茶飲料の需要の伸びに呼応する形で、平成16年まで上昇しましたが、その後の需要の停滞により、荒茶価格も低迷しています。
お茶の価格については、ペットボトル緑茶飲料の需要の伸びに呼応する形で、平成16年まで上昇しましたが、その後の需要の停滞により、荒茶価格も低迷しています。
また、お茶の価格は①茶種による価格差、②茶期による価格差等が大きく、これに品質に応じた価格差が加わるため、農家によっては売上・利益に大きな差がついています。
緑茶の消費量について、緑茶(リーフ茶)は減少傾向で推移していましたが、近年は横ばいとなっています。一方、ペットボトル入り緑茶は増加傾向で推移しています(図4参照)。
図4を見ると、お茶全体の1世帯当たりの年間支出金額の合計は、約1万円で推移していますが、緑茶(リーフ茶)と茶飲料(ペットボトル)の支出金額が逆転するなど簡便なペットボトルでの飲用にシフトしていることがわかります。
一方、炭酸飲料、ミネラルウォーター類は、消費が拡大するなど、お茶以外の飲料の伸びが顕著となっています。(データは示していない)
 さて、以上のようにお茶農家の状況は大変厳しく、お茶農家向けにお茶の加熱乾燥機械(火入れ機械)を製造販売しているC社の売上も低迷しており、厳しい状況に置かれていました。
さて、以上のようにお茶農家の状況は大変厳しく、お茶農家向けにお茶の加熱乾燥機械(火入れ機械)を製造販売しているC社の売上も低迷しており、厳しい状況に置かれていました。
C社は従業員数20名ほどのお茶の生葉を熱乾燥して荒茶にする加熱乾燥機械を製造・販売する会社です。顧客はお茶農家であり、お茶用ペットボトルを製造する大手メーカー向けの機械ではありません。
荒茶の出荷を示した図5をみても2012年をピークに出荷金額と数量が減少していることがわかります。
今後ともこのような傾向は継続すると考えられ、社長は今後の事業展開について大いに悩んでいました。
ここで、C社が取りうる戦略は大きく分けて2通りあります。
- 既存のお茶市場で生き残り、競合他社がなくなるのを待ち残存者利益を得る市場深耕戦略
- 新たな市場を開拓して、新規事業を立ち上げる新市場開拓戦略
C社の社長は、このままお茶の市場で生き残りをかけても将来の展望が開けないと考え、新たな市場へと打って出ることを考えました。
- C社の強みは装置の小型化と独自の加熱方法にある
C社のように他分野に進出する際にまずやるべきことは自分の強みを客観的に理解することです。
C社は技術力に磨きをかけ続けており、ユニークな茶葉乾燥装置を開発し、特許も複数取得していたため特許を活用してC社の強みを見出してみました。
やり方は、C社が出願した特許と同じ分類(特許出願をすると特許庁により複数の分類記号がつけられる)に他の企業がどれくらいいるかを調べます。その中で、C社の比率が高い分類はC社の競争力も高いと推測することができます。
以上から作成したグラフが図5です。そのグラフからC社の強みは以下の点であることがわかります。
- 被乾燥物が曲がりくねって運動するもの
- 輻射によるもの
- 乾燥温度分布の均一化、または均一な加熱
- バーナー
- ベルトコンベア
即ち、①から「装置の小型化」、②、③、④から「独自な手法による均一な温度による加熱」、⑤から「連続加熱方法」が強みであることがわかります。
- 自社の強みから自社技術の新たな市場(転用先)を探す
自社の強みがわかったら、次に自社の技術力を展開できそうな分野を調査します。
やり方は、C社の強みの特徴的なポイント(記号)を用いて特許情報から技術や商品を抽出するというものです。
以上のような特徴を元にして特許情報調査を行い、どのような分野で乾燥装置が用いられているかをまとめたものが図7です。
やはり多いのは食品関連で、野菜類、穀物類、魚類、海産物類です。また、茶葉に用いられる用途も全体の1割ほど見られました。
変わったところでは食品廃棄物(食品残渣)やその他の廃棄物の処理に使用される乾燥機というのもありました。廃棄物は多くの水分を含んでいるため乾燥させて重量を減らし廃棄コストを削減するのです。
それ以外にも粉体を製造するための乾燥装置というのも多く見られました。粉体にして食品に加工するものが多かったのです。
これらの中で特に注目したのが薬剤関連です。世の中には多くの薬剤がありますが、乾燥固定を含むものが多く見られたのです。そこで薬剤関連についてさらに深く調査をしました。
- 植物由来の薬剤が新分野としての候補
 参入可能性のある市場を見出す際に、まず重要なのは以下の二点です。
参入可能性のある市場を見出す際に、まず重要なのは以下の二点です。
- 自社の技術が活きるか
- 自社の商品との関連性があるか
自社の技術が生きないのであれば一から技術を習得しなければならず時間がかかります。時間がかかることは避けるべきです。
自社の商品と関連性が低いと、何をどうしていいか全くわからず、手探りで進むことになります。また、商品ができたとしてもピントのずれたものになりがちです。
C社としては「加熱乾燥技術」と、「加熱加工した茶葉」という2つの技術と商品が活きる分野が好ましいことになります。
ここで、特許分析のやり方は、C社の技術的な強みのポイント(記号)と茶葉の記号と、薬剤の記号を用いて特許情報から商品分野を抽出するというものです。(図8)
以上の結果から、「植物物質含有医薬品」及び「香料」という分野が見つかりました。この分野をポジショニングマップ化して市場を概観すると図9のようになります。
 加熱乾燥は単に水分を除去するもの(食材の乾燥等)と化学反応を伴い、機能や効能を向上させるものに大別することができます。
加熱乾燥は単に水分を除去するもの(食材の乾燥等)と化学反応を伴い、機能や効能を向上させるものに大別することができます。
当社が今まで行ってきた茶葉の乾燥(火入れ)もある種の化学反応を伴い、お茶の味を良くするものでした。したがって、当社の技術はポジショニングマップの右上に位置しているといえます。
さらに機能や効能を向上させるものには自然素材を用いた香料や植物を用いた医薬品(漢方薬など)があります。
その結果、当社の技術を活かすには「植物物質含有医薬品」方面へ進出することが良いだろうという話になりました。
- 植物含有医薬品に関する今後の市場は期待できそう
植物由来の医薬品に関する特許出願人と出願年を図10に示します。毎年ある程度の特許出願があり、ある程度活発品市場であることがわかります。大企業も出願人として名を連ねており、今後の市場の成長も期待できそうです。
<出願企業の特徴>
出願人の第一位は東洋新薬という会社です。この会社は九州に本社があり、資本金5千万円、社員約800人の会社ですが、健康食品事業や化粧品事業に力を入れている会社です。2000年からまんべんなく特許出願を行っており、この分野に絞った開発をしていることがわかります。
近年出願が多いのは、花王、資生堂ライフサイエンス、エステーなどです。健康食品や健康グッズに注力している会社であることがわかります。誰でも知っている大企業であり、この分野が将来有望ということで研究開発をしているようです。
C社は機械製造メーカーであるため医薬品の製造を行うわけではありません。そのため、パートナーまたは顧客となる会社を見出し装置を販売することが目的です。そう考えると、大手・中堅企業がある程度存在するこの市場は当社の目的にかなっていると言えるでしょう。
- 植物含有医薬品はC社の技術が活きる分野
先程の特許情報を分析して、縦軸に医薬品の目的を、横軸に手段を取ると図11になります。
目的は色々とありますが、一番注力されている(図のバブルが大きい)目的は「新薬効の発現」です。その目的を達成するための手段として一番多く使われているのが「加熱又は冷却又は加圧による」ものです。「加熱又は冷却」というのはC社の装置の強みとしてあげられるものであり、この分野との相性が良いことが推測できます。
以上より、この分野はC社の技術が活かせそうな分野であると言えそうです。現在、更に調査を進めてどのように当社の機械が活用できるか、具体的に取り組むべき商品はどのようなものかという検討をしている段階です。
<結論>
- 以上見てきたように、当社の得意分野である小型加熱乾燥装置を、植物性原料に活用できる分野として植物物質含有医薬品分野が見つかりました。特許の出願件数もほどほど存在し、目的である「新薬効の発現」に「加熱又は冷却手段」を用いている点も当社の技術をいかせる可能性がありそうです。
- さらに特許を分析することで、「どのような装置を用いているか」、「どのような商品を作っているか」、「より具体的な課題は何か」などを知ることができます。
- なお、香料については時間の関係上調査を割愛しましたが、天然香料素材は植物であり、素材を加熱することでより香味・風味を増加させる特許が存在します。この分野も新分野としての可能性がありそうです。
良い技術を持ちながら、業界全体が低迷しているため苦境に立っている中小企業は多く存在します。その際に重要なのは自社の技術がどの分野・市場で活用できるかという目利きです。
このように、弊社が開発した特許情報と市場情報とを組み合わせた「スキマ商品・ニッチ市場」を見いだす手法は、「勝てる市場の探索」と「新商品開発」に、視野を広げ、新たな気づきを与えてくれるツールとして非常に有効です。
以上